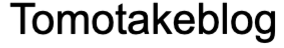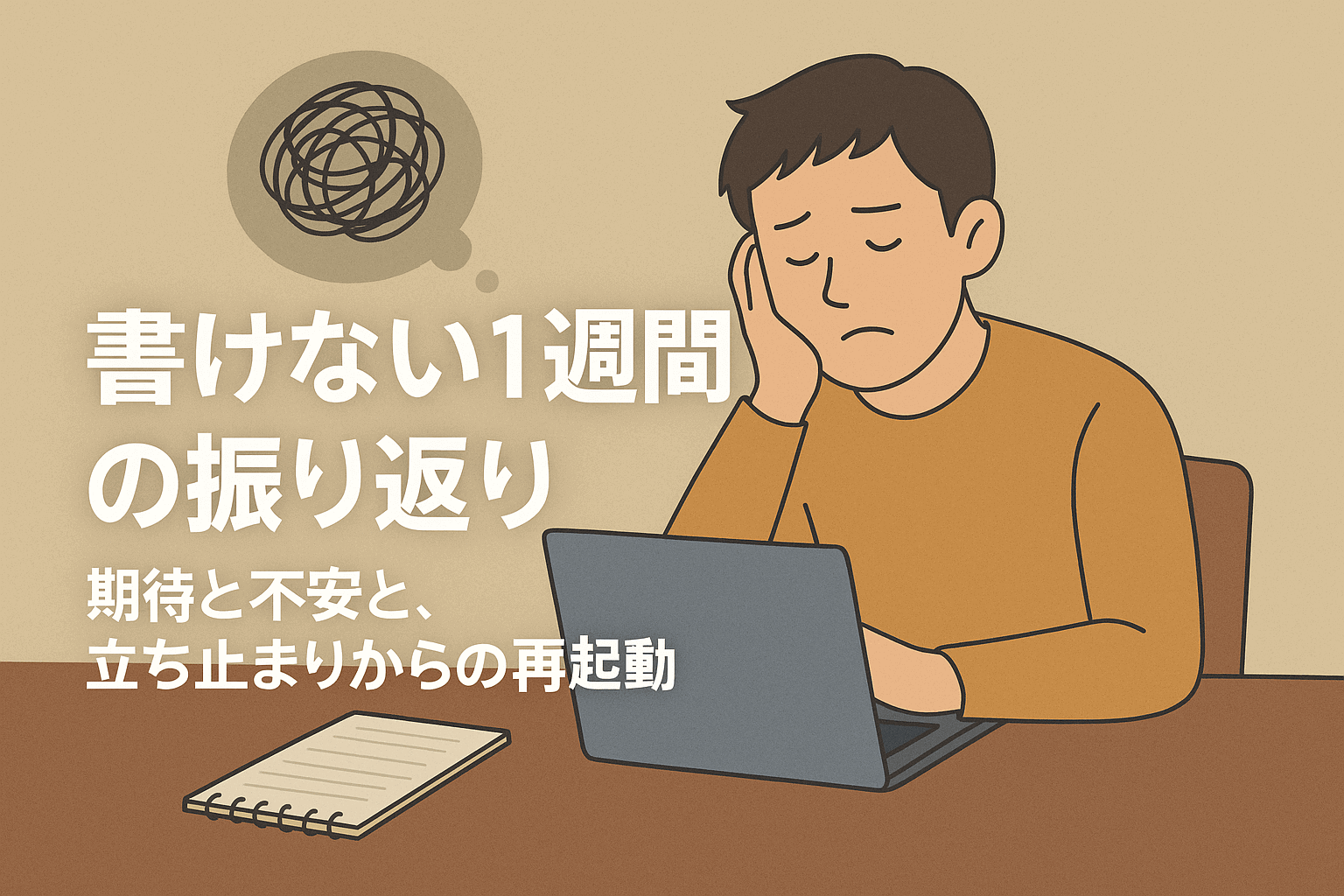書けない1週間の振り返り【期待と不安と、立ち止まりからの再起動】
「また書けなかった」
「記事が進まない」
これは初めての悩みではない。
だけど今回は、少し違う“引っかかり”に気づいた。
記事を書くたびに現れる「詰まり」は、単なるスキルの問題ではなく環境・関係性・期待値など、より複雑な文脈と絡んでいた。
この記事は、書けなかった1週間を振り返りながら、どこで詰まり、どう立て直すかを探る試みである。
もくじ
- なぜ“支援ツール”がプレッシャーになるのか?
- アウトプットの流れが止まると、なぜ内省も止まるのか?
- 支援と束縛のあいだにある“プログラムの違和感”
- 思考が止まったら、「小さく書く」が再起動のスイッチになる
- “繰り返し書けない”は、内省の深まりかもしれない
- 読者への問いかけ
- まとめ:再起動の一歩は、未完成のままでも動くこと
- 次のアクション(自分へのメモ)
なぜ“支援ツール”がプレッシャーになるのか?
補助のはずのAIが書けなさを加速させた理由
記事制作のプロセスで感じていたのは、次のような見えないプレッシャーだった。
・GPTsで出力すると容量が多くなり、整えきれない
・「YouTubeや図解を挟まないと価値がない」と感じてしまい、動きが止まる
・「誰かの期待に応えないと」と思うほど、自分の言葉が遠のいていく
何を、誰に、どこまで書けば良いのか。
この曖昧さが「書けない」状態を引き延ばしていた。
アウトプットの流れが止まると、なぜ内省も止まるのか?
普段は、
自分で考える → GPTに投げる → 修正 → 投稿
という流れで制作しているが、構成や画像が揃わないと手が止まる。
すると、「やっぱり自分にはスキルがないのでは」と思考が内向してしまう。
本来なら補助であるはずのAIが、
「これって本当に読める構成なの?」
「画像もつけないと情報が薄い?」
と自問を加速させ、
完成度へのプレッシャーに変わっていたのかもしれない。
実際にこのループに陥ることはしばしば起こるのである。
支援と束縛のあいだにある“プログラムの違和感”
行動習慣のサポートとして参加していた週刊プログラムにも、今は少し距離を感じている。
・報告しても反応が薄く、温度を感じない
・提出義務のような空気感があり、行動の意味を見失う
「これって、誰のためにやってるんだろう?」と迷いが生まれていた。
サポートは限定的で、習慣化のためのスケジュールの組み立て、週一のフィードバックと軌道修正だけである。私は、管理をしているようには感じられず、顧客目線では運営が難しいのでしょう。
それも体験してみないと分からないものです。
思考が止まったら、「小さく書く」が再起動のスイッチになる
振り返ってみると、完璧な準備や構成よりも、「まずは出す」という行動の火種が必要だったと気づく。
・3記事書き上げる
・AIも資料も“完璧に揃えない”ことを前提にする
・書けない理由を観察しつつ、出すことで前に進める
考えすぎて止まるより、荒削りでも動いた方が思考も感覚も整ってくる。
【繰り返し書けない】は、内省の深まりかもしれない
「また書けない」と感じるたびに「前に進めていない」と思ってしまう。でも実際は、
・前回とは“違う場所”でつまずいている
・“同じテーマ”でも、視点が深まってきている
書けないを繰り返すことは、「同じことに悩むバカらしさ」ではなく、“定点観測”という価値ある習慣なのかもしれない。
繰り返しつまずくことで、見え方は少しずつ変わってくる。
・つまずくことに、早く気づくよううになる
・どうして、つまずいたかを言語化できる
・つまずいた後、どう改善するかを考えるようになる
繰り返しているようで、実際は小さな変化が起きているんです。
問いかけ
⬜︎あなたは今、「誰のために」「何のために」書こうとしていますか?
⬜︎同じように“書けなさ”を感じたとき、それはどんなプレッシャーでしたか?
⬜︎「またここに戻ってきた」と感じるとき、どんな気づきがありましたか?
⬜︎その「戻ってくるテーマ」は、あなたにとってどんな意味があると思いますか?
まとめ:再起動の一歩は、未完成のままでも動くこと
今回の振り返りを通して、自分にとって必要なのは「完成」ではなく、「未完成でも動き続ける流れ」だったと気づいた。
行動の火が消えそうなとき、再起動のスイッチは、小さなアウトプットにある。
「思考整理」「振返り」これもまた、小さなアウトプットで次へのスイッチです。
次のアクション(自分へのメモ)
・来週中に3記事仕上げる(テーマはこだわりすぎず)
・情報収集に迷ったら「一旦出す」→「後から整える」の順で動く
・プログラムは「使うか、離れるか」を判断する準備をしておく