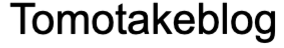相手の気持ちがわからないときに読むMBTI×発達段階の整理法
「相手を理解できない」
「人間関係に疲れた…」
と感じることはありませんか?
職場や家庭、友人関係のなかで
・どうしても相手の考え方が理解できない
・会話しても噛み合わない
・自分が悪いのでは?と落ち込む
といったモヤモヤを抱えるのは、とてもつらいものです。
この背景には、MBTI(性格タイプ)による認知の違いや、成人発達理論でいう「発達段階3.5」特有の心理的な揺らぎが関係していることがあります。
この記事でわかること
-
□ MBTIタイプの違いが人間関係のすれ違いを生む理由
□ 発達段階3.5で「相手を理解できない」と感じやすくなる仕組み
□ 余裕を取り戻すための3つのアプローチ
大切なのは「相手を変えること」ではなく、自分の認知や段階を理解し、関係の捉え方を整えることです。
この記事を読めば、人間関係のストレスを軽くし、少しずつ余裕を取り戻すヒントが見つかります。
(※当サイトは、アフィリエイト広告を利用しています)
もくじ
- なぜ「相手を理解できない」気持ちが強くなるのか?
・自分の価値観の枠組みが強く働いている
・相手の背景や段階を想像できないと、ズレが広がる
・「理解できない」気持ち自体が悪いわけではない - MBTIタイプの違いが生む“すれ違い”の構造
・情報の取り方(SとN)の違い
・判断の仕方(TとF)の違い
・外向(E)と内向(I)の違いも影響する
・違いは“敵”ではなく“レンズの差” - 発達段階3.5で起こりやすい“相手への違和感”
・「相手を理解できない」という強い感覚
・自己理解の浅さが対人関係に影響する
・違和感は“成長のサイン”でもある - 違和感をやわらげるためにできること
①「理解できない」と決めつけない
②自分の感情を整理する
③小さな「共通点」を見つける
④必要なら距離を取ってもいい - 発達段階3.5を乗り越えるヒント
①「正解探し」から「問いかけ」へシフトする
②自己理解を深めるツールを活用する
③「サポートしてくれる人」を見つける
④少し先の未来に目を向ける - まとめ|違和感は成長のサイン
自分の状態を整理するためのチェックリスト
次の一歩は「安心できる場づくり」
最後に
1:なぜ「相手を理解できない」気持ちが強くなるのか?
人間関係の中で「どうしても相手の考えや行動が理解できない」という瞬間は誰にでもあります。
特に日常的に接する家族やパートナー、職場の同僚であれば、その感情はさらに強くなるでしょう。
ではなぜ、そんな「理解できない」という気持ちが生まれるのでしょうか?
自分の価値観の枠組みが強く働いている
私たちは、誰もが自分の価値観や経験をベースに物事を解釈しています。
MBTIでいう主機能(最も信頼している認知のスタイル)は、情報を取り入れたり判断する際の自分なりのレンズとして機能します。
このレンズが無意識に働くため、相手が自分と全く違うレンズを持っていると、
「なんでそんなことをするの?」
「私なら絶対にそうしない」
と感じやすくなります。
相手の背景や段階を想像できないと、ズレが広がる
MBTIのタイプ差や成人発達段階の違いは、行動の背景にある考え方や価値観の差を生みます。
・MBTI:情報の取り方・判断の仕方の違い
・発達段階:どの世界観(コンクリートかサトルか)に軸足を置いているか
これらが重なると、相手の行動がまるで「意味不明」に見えることもあります。
特に、自分と相手が違う世界観に立っているときは、相手の言動を誤解しやすいのです。
「理解できない」気持ち自体が悪いわけではない
大切なのは、「理解できない=関係が破綻する」ではないということです。
理解できない気持ちは、自分の価値観やレンズを知るきっかけにもなります。
・なぜ自分はそう感じるのか?
・相手はどのような価値観で動いているのか?
この問いを持つことが、相手を理解する第一歩になります。
MBTIタイプの違いが生む“すれ違い”の構造
「相手が理解できない」という気持ちの裏側には、MBTIタイプによる認知の違いが隠れています。
ここでは、すれ違いが生まれる代表的なパターンを整理します。
情報の取り方(SとN)の違い
MBTIでは、情報をどう取り入れるかのスタイルが S(感覚)とN(直観) に分かれます。
Sタイプ(感覚)
・現実的・具体的な情報を重視
・過去の経験や事実をもとに考える
・「今・ここ」でわかることに安心感を覚える
Nタイプ(直観)
・未来や可能性、パターンを重視
・現状を超えたつながりや意味を見出す
・「これからどうなるか」に意識が向きやすい
この違いがあると、
Nタイプの人が未来の話をしてもSタイプには「根拠がない」と見えることがあり
逆に
Sタイプが目の前の事実を語ってもNタイプには「夢がない」と映ることがあります。
判断の仕方(TとF)の違い
次に、判断をどのように下すかという違いです。
Tタイプ(思考)
・論理的・合理的な判断を重視
・客観的な基準をもとに結論を出す
Fタイプ(感情)
・人の気持ちや価値観を重視
・関係性や場の調和を優先する
Tタイプからすると、Fタイプの判断は「感情的すぎる」と見えることがあります。
逆に
Fタイプからすると、Tタイプの判断は「冷たい・思いやりがない」と感じられることが多いです。
外向(E)と内向(I)の違いも影響する
E(外向)とI(内向)はエネルギーの方向性の違いです。
・Eタイプは話しながら整理し、外の刺激から元気を得る(からだの外側)
・Iタイプは考えてから話す傾向があり、一人で内省する時間が必要(からだの内側)
この違いがあると、
Eタイプは「Iタイプが何を考えているのかわからない」と感じやすく、
Iタイプは「Eタイプが自分の領域に踏み込んでくる」と感じやすいのです。
違いは“敵”ではなく“レンズの差”
これらの違いは、優劣ではなくレンズの差です。
しかし、違いに気づかないままコミュニケーションを続けると、
「どうしてわかってくれないの?」
「自分が間違っているのかも」
という誤解や自己否定につながりやすくなります。
発達段階3.5で起こりやすい“相手への違和感”
成人発達理論では、発達段階3.5(コンクリートからサトルへの移行期) にある人は、他者や自分の内面に対して「違和感」を覚えやすいといわれます。
「相手を理解できない」という強い感覚
3.5の段階では、これまでの価値観(コンクリート)が崩れつつある一方で、次の段階(サトル)に完全に移行できていない状態です。
・相手の言動に対して「なぜそんなことをするの?」と感じやすい
・自分の考えに自信が持てず、相手に合わせすぎたり逆に反発したりする
・「正しい」「間違っている」という二元的な思考に揺れやすい
この「相手を理解できない」という感覚が、コミュニケーションのすれ違いを大きくします。
自己理解の浅さが対人関係に影響する
3.5の段階では、まだ自分の価値観や感情の正体を言語化しきれないため、
自分の気持ちをうまく伝えられない
相手に誤解されやすい
「わかってもらえない」と孤立感を抱きやすい
といったことが起きやすくなります。
違和感は“成長のサイン”でもある
この段階での違和感は、決して悪いものではありません。
自分や相手を「理解したい」という気持ちが芽生え始めている証拠でもあります。
・相手の背景や価値観を想像する
・自分がなぜモヤモヤしているのか内省する
こうしたプロセスが、3.5から次の発達段階(4.0)へ進むきっかけになります。
違和感をやわらげるためにできること
発達段階3.5で感じやすい「相手を理解できない」という違和感は、放置すると関係性の断絶や孤立感につながりかねません。
ここでは、違和感をやわらげるためにできる具体的な行動を整理し、実際のケーススタディも交えて解説します。
①「理解できない」と決めつけない
違和感が強いときは、つい「この人とは分かり合えない」と思いがちです。
しかし、これは自分の内面を守るための防衛反応であることも少なくありません。
・「相手には相手の見えている世界がある」と意識する
・「わからない=悪いこと」ではないと認識する
・距離を置くのではなく、少しずつ背景を知る
ケーススタディ:価値観の違いで衝突したAさん
Aさんは職場の同僚Bさんの行動に違和感を覚え、「何を考えているのか分からない」と苛立っていました。
しかし、Bさんに直接話を聞いてみると、仕事に対する優先順位や背景が自分とは全く異なることを知り、「理解できない」と決めつけていたことに気づきました。
この経験からAさんは、「わからないまま関わり続ける」余裕を少し持てるようになったと言います。
②自分の感情を整理する
違和感の正体は、多くの場合「自分の価値観や期待に触れたから」生じています。
自分の内側を整理すると、相手への見方も変わってきます。
・なぜモヤモヤするのか、紙やノートに書き出す
・「私はどうしたいのか?」を一度立ち止まって考える
・必要に応じて信頼できる人に話を聞いてもらう
ケーススタディ:モヤモヤの正体に気づいたCさん
Cさんは友人が自分の予定を優先してくれないことに腹立たしさを感じていました。
感情を書き出してみたところ、「自分の存在を軽く扱われた」と感じていることが分かりました。
この気づきをもとに友人に率直に伝えると、相手も「そんなつもりはなかった」と謝罪。
感情を整理することで関係が改善しました。
③小さな「共通点」を見つける
相手と自分の違いばかりに目を向けていると、距離が広がってしまいます。
・好きなもの、関心があるものを探してみる
・相手が大切にしている価値観を知ろうとする
・自分ができる小さな協力やサポートをしてみる
ケーススタディ:共通の趣味で距離が縮まったDさん
Dさんは同僚との会話がかみ合わず、「この人とは合わない」と思っていました。
しかし、ある日ランチの席で共通の趣味があることが分かり、一気に距離が縮まりました。仕事のやり取りもスムーズになり、「違いを埋めるのではなく、共通点を見つけることが大切」と実感したそうです。
④必要なら距離を取ってもいい
どうしても違和感が強く、心身が疲れてしまう場合は、一時的に距離を取ることも選択肢です。
・無理に相手を理解しようとしない
・一人で過ごす時間や趣味に没頭する時間を持つ
・自分が安心できる人や環境を優先する
ケーススタディ:距離を取ったことで関係が良くなったEさん
Eさんは家族との価値観の違いに疲れ、常に苛立ちを抱えていました。
思い切って週末を一人で過ごすようにしたところ、気持ちが落ち着き、以前より冷静に家族と接することができるようになりました。
距離を取ることで「相手に優しくできる余白」ができたのです。
自分視点だけに捉われずに、相手の視点を見ようとすること、また直接話す場を設けることは誤解を解消する上でとても重要です。
注意としては、ニュートラル(健全、先入観を手放した状態)で関わることが大切です。
発達段階3.5を乗り越えるヒント
発達段階3.5は「これまでの価値観が揺さぶられ、新しい視点に気づき始める移行期」ともいえます。
違和感や葛藤が増えるのは自然なことですが、この時期をどう過ごすかによって次の成長の質が変わります。
ここでは、3.5を乗り越えるためのヒントを整理します。
①「正解探し」から「問いかけ」へシフトする
3.5では「自分が正しいのか」「相手が間違っているのか」という二項対立に陥りやすい時期です。
・「正しい答えは何か?」ではなく「どうしてそう考えるのか?」と問いかける
・相手の背景や価値観に目を向ける
・白黒つけないまま「一旦置く」感覚を持つ
小さな疑問を持ち続けることが、次の成長につながります。
②自己理解を深めるツールを活用する
自分を客観的に知ることができると、他者の違いも受け入れやすくなります。
・MBTIやエニアグラムなど、認知や価値観の傾向がわかるツールを活用
・自分の発達段階や課題を整理できるワークショップや研修に参加
・日記やジャーナリングで感情や価値観を書き出す
自己理解が深まると「違いがあってもいい」という余白が生まれます。
③「サポートしてくれる人」を見つける
3.5の葛藤は一人で抱え込むと辛くなりがちです。
・安心できる友人や先輩に相談する
・専門家(カウンセラーやコーチ)に話を聞いてもらう
・同じ課題を抱える仲間と学び合うコミュニティに入る
他者の存在が「違いを受け入れる」練習の場にもなります。
④少し先の未来に目を向ける
3.5は現在の価値観が揺らぐため、目の前の不安や違和感に意識が向きがちです。
・3年後・5年後の自分をイメージする
・今の経験が未来でどう役立つかを考える
・小さな目標を決めて一歩ずつ進める
長期的な視点を持つと、目の前の葛藤も「成長のプロセス」として受け入れやすくなります。
まとめ|違和感は成長のサイン
人間関係に疲れを感じたり、相手を理解できない自分に落ち込むことは、誰にでもあるものです。
しかしその違和感は、発達段階が次のステージに移ろうとしているサインかもしれません。
・これまでの価値観が揺らぎ、迷いを感じる
・相手の考え方や行動が理解できずにモヤモヤする
・自分の考えも、相手の考えも正しいように思えて決めきれない
こうした葛藤は、成長のプロセスで避けて通れないものです。
「自分はダメだ」ではなく、「今は整理の時期なんだ」と受け止めることができれば、心の余裕が生まれます。
自分の状態を整理するためのチェックリスト
以下のチェックリストに当てはまるものがあるか確認してみましょう。
当てはまる項目が多いほど、心のバランスが揺らいでいる可能性があります。
・相手の行動や言葉が過剰に気になる
・「自分ばかり我慢している」と感じる
・相手の価値観を否定したくなる自分がいる
・これまで大切だと思っていた価値観が揺らいでいる
・「自分の考えが正しいのか」自信がなくなってきた
このような状態は、新しい価値観や視点を取り入れる準備が整ってきているサインです。
ポイント
3.5の時期は「迷い」と「違和感」が強くなりやすいのが特徴です。
この時期をうまく乗り越えるには、安心できる環境で自分の考えを整理し、少しずつ視野を広げていくことが大切です。
次の一歩は「安心できる場づくり」
発達段階3.5の移行期は、1人で抱え込まずに話せる場を持つことがとても大切です。
・安心して話せる友人やコミュニティ
・カウンセリングやコーチングなどの外部サポート
・日記やアウトプットで自分の考えを整理する習慣
違和感を成長のきっかけに変えるには、安心できる環境が不可欠です。
最後に
この時期に経験する「人間関係のモヤモヤ」「自分の中の揺らぎ」は、
決して後退ではなく、大きな成長への通過点です。
もし1人で抱え込みすぎて辛くなったときは、誰かに相談してみてください。
信頼できる人や専門家の力を借りることも、立派な前進です。
補足:専門家や支援を頼る選択も
人間関係のモヤモヤ、自分では立て直せないと感じるときは、専門家のサポートを受けることも大切です。
・心理カウンセラーやメンタルクリニックに相談する
・職場や学校の相談窓口を利用する
・信頼できる第三者に話を聞いてもらう
「でも、身近に相談できる人がいない」「対面はハードルが高い」という方へ
自宅から匿名で相談できるココナラ占い・カウンセリングを試してみるのもひとつの方法です。
登録は無料で、オンラインで1対1の相談ができるため、気軽に話を整理できます。
※初回はクーポンもあり、安心して始められます。
心理カウンセリングやお悩み相談カテゴリも充実しているので、「自分の気持ちを整理したい」と思ったときに役立ちます。
「弱いから頼る」のではなく、よりよい自分を取り戻すための手段のひとつとして考えましょう。
関連記事:最も遠い認知スタイルと出会うことで、自己理解が深まった話ー INTJとESFPの違いを通じて見えた、自分と他者の関係性