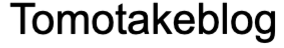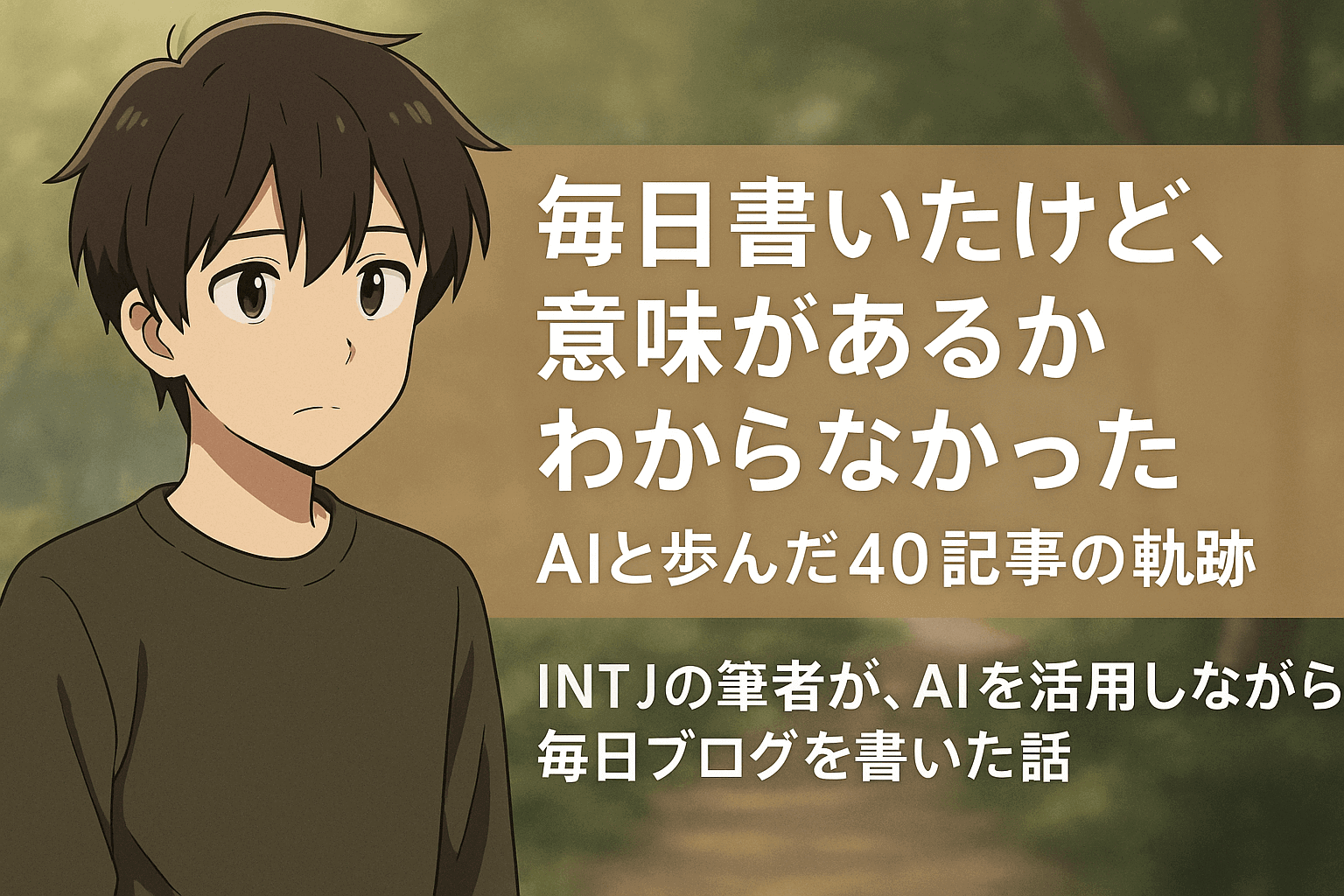「毎日書いたけど、意味があるかわからなかった」、AIと歩んだ40記事の軌跡
これは、PVが伸びたとか、収益が出たとか、そのような話ではありません。
もっと地味で、もっと個人的な話です。
「毎日ブログを投稿してきたけれど、正直なところ、意味があるのかはまだよくわからない」
そんな気持ちを抱えながら、でもなぜか言葉を紡ぎ続けてきました。
その途中で出会ったのが、AIという伴走者でした。
この記事では、INTJというタイプ特性をもつわたしが、どんな思考でこのブログを積み上げ、どんな葛藤を経てきたか。
そしてこれから何を紡いでいこうとしているのかを、ひとつずつ丁寧に言葉にしていこうと思います。
もくじ
- はじめに:これは“成功者の振り返り”ではない
- 1. 「書けるけど、まとめられない」わたしのタイプ
・INTJの特性と“書けない問題”
・「完璧にまとめよう」として止まるクセ - 2. AIという補助輪が、アウトプットの流れを変えた
・書きたいことはある、でも形にできない
・AIとの対話で「自分の言葉に近づけた」感覚 - 3. 40記事でわかった“続けること”の正体
・価値が見えないまま、積み上がるもの
・「これは誰かに届いているか?」という問い - 4. 「伝わらないこと」の背景にあった、タイプと認知の違い
・1分の話が伝わらない事例から見えた本質
・認知スタイルの違いが、コミュニケーションのすれ違いを生む - 5. これからの展開:言葉を整える習慣としてのブログ
・自己理解×思考整理×発信=知の習慣
・「共感」よりも「発見」を届ける場所へ - おわりに:エッセンスは、たとえ完全でなくても届く
1. 「書けるけど、まとめられない」わたしのタイプ
わたしは、思考をめぐらせることが好きなタイプです。
MBTIでいうとINTJ。
内向的な直観(Ni)を主機能にもち、外に出す前に「構造」を組み立てようとします。
だから、アウトプットはできる。
ただし、それが“まとまり”を持ったものとして、他者に伝えられる形になっているかどうか。
ここに、ずっと悩みがありました。
「言語化はできる。でも、整理して“届ける形”にするのが苦手」
そう気づいたのは、音声メモを毎朝とっている自分を見たときです。
話すことはできる。
でも、書くとなるとまとまらない。考えすぎて止まってしまう。
完璧主義、構造主義、意味のないものは出したくない。そんな性質が重なって、「出せない自分」が生まれていました。
INTJがブログ発信でつまずきやすいポイント
・書けるが、構造がまとまらない
・完璧を求めるあまり、投稿までたどりつかない
・外に出すよりも、内面で熟成する傾向が強い
2. AIという補助輪が、アウトプットの流れを変えた
そんな中で出会ったのがAIでした。最初は正直、少し抵抗もありました。
「それって、自分で書いたと言えるのかな?」
「AIに頼ったら、自分らしさが薄れるんじゃないか?」
でも、ある日気づいたんです。AIは、わたしの代わりに書いているのではなく、わたしの思考を“形にしてくれている”のだと。
言葉にならない“ニュアンス”や“文脈”を、そっと拾い上げて、整えてくれる存在。
「そう、それが言いたかったんだよ」
そんな風に感じることが増えていきました。AIとの対話を通して、ようやく“わたしの言葉”が世界に出ていく実感が持てるようになってきたんです。
完璧ではないけれど、エッセンスは伝わっている。
それでいい。
そう思えるようになってから、投稿のリズムが変わりました。
AI活用で得られた3つの変化
| 変化 | 内容 |
| 1 | 言語化に対するストレスの軽減 |
| 2 | 構造的な整理ができるようになった |
| 3 | 「伝える」ことへの心理的ハードルが下がった |
3. 40記事でわかった“続けること”の正体
最初の10記事くらいは、正直よくわからないまま書いていました。
「これでいいのかな?」という手探りの毎日。
20記事を超えたあたりで、「あ、これは自分の地図を作っているんだな」と感じはじめ、
30記事あたりでは「これは誰かに届いているのかもしれない」と思える瞬間が出てきました。
40記事目に差しかかる今、ようやく「続ける意味」が少しずつ実感として持てるようになってきています。
それは、PVや反応ではありません。
・思考を整理する力がついてきたこと
・感情と距離を取って観察できるようになったこと
・「届けよう」と思えるようになったこと
何より、「わたし自身の中に少し余白ができた」こと。
続けたことで得られたのは、“自分に対する信頼”だった。
4. 「伝わらないこと」の背景にあった、タイプと認知の違い
最近、とても印象的な出来事がありました。
あるワークで、1分間の出来事を人に話してもらい、それを聞いた人が「何を伝えたかったのか?」を説明するというもの。
その後、話し手が「実際に伝えたかったこと」を伝える。
すると、驚くほど“ズレていた”のです。
「1分しか話していないから仕方ない」と言えばそれまで。
でも、その“ズレ”の背景には、相手の認知スタイルや、情報の受け取り方の違いが関係していることにも気づきました。
伝えたつもり、伝わったつもり。
でも、実際には届いていない。
これは、言葉を発信するうえでも、とても大事な気づきでした。
認知の違いは、“誤解”ではなく“ズレの存在”と捉えることで、対話が深まる。
「ちゃんと伝わっているかな?」
「この表現は、相手のレンズでどう映るかな?」
そういう視点を持てるようになったことで、自分の発信も少し変わった気がしています。
5. これからの展開:言葉を整える習慣としてのブログ
これからも、「うまく言えないけど、言いたいことがある」わたし自身のままで、発信を続けていこうと思います。
キレイに整った言葉じゃなくていい。
完璧な構造じゃなくていい。
でも、そこに“伝えたい気持ち”と“少しの工夫”があれば、それは誰かの気づきになるかもしれない。
このブログは、検索順位を狙うものでもなければ、誰かを説得するためのものでもありません。
「自分の思考を整えるための習慣」
そしてそれが、結果的に誰かの「視点のきっかけ」になれば、こんなに嬉しいことはありません。
おわりに:エッセンスは、たとえ完全でなくても届く
AIを使うことに賛否はあるかもしれません。
でも、わたしにとっては、ようやく「まとめる」「出す」「伝える」ができるようになったという意味で、とても大きな変化でした。
すべてが自分の言葉じゃないかもしれない。
でも、そこに“わたしのエッセンス”が宿っていれば、それでいい。
そう思えるようになった今、ようやく本当の意味で「書くこと」がわたしの中に根づいてきた気がします。
そして、これからもこの場所で、言葉を育てていこうと思います。