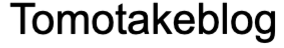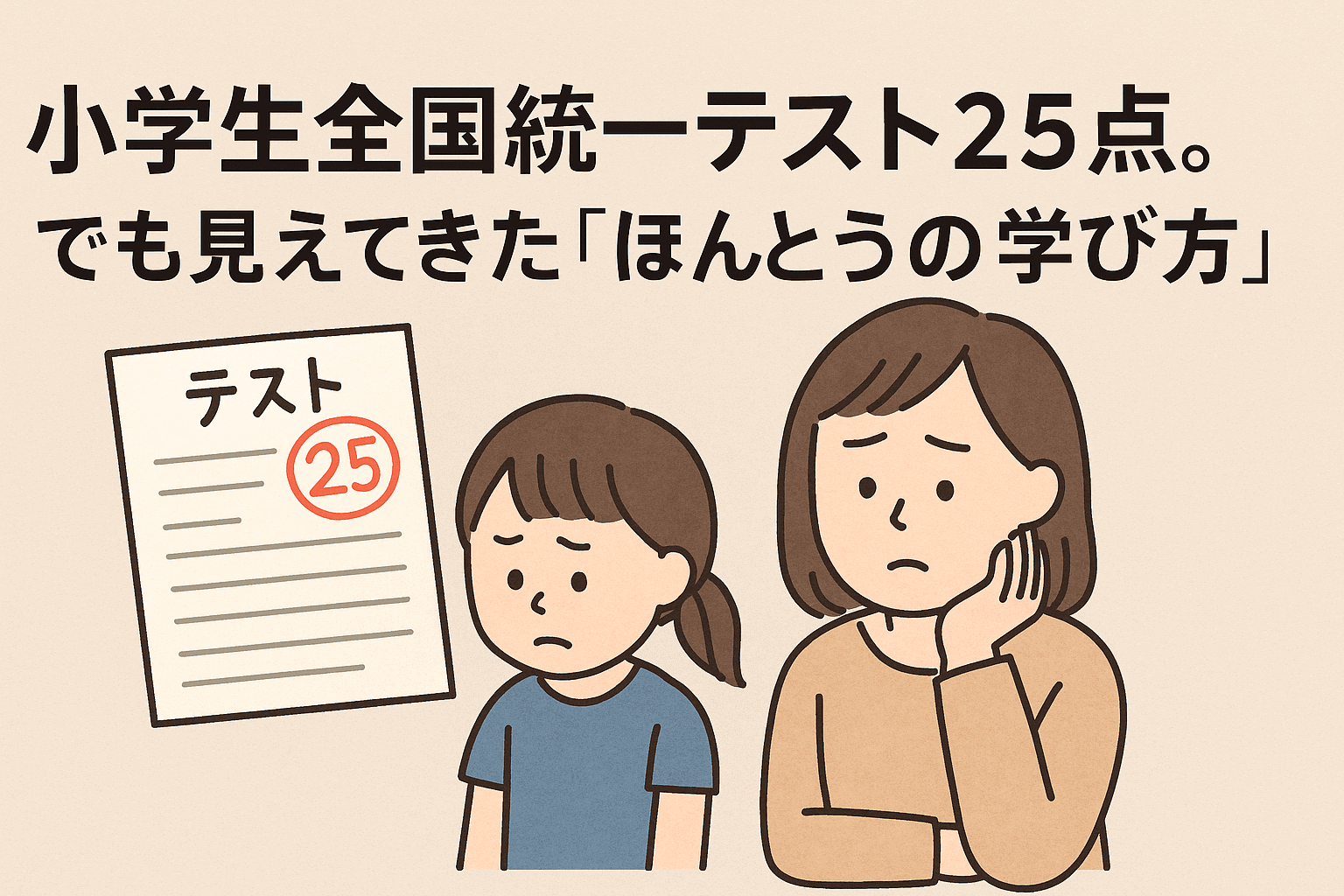全国統一小学生テスト25点「でも見えてきた!ほんとうの学び方」
先日、塾の先生と面談をしました。テーマは、小学生全国統一テストの結果と、これからの学びについてです。
テスト結果は300点満点中25点。数字だけを見ると「厳しい」と思うかもしれません。でも、今回の面談で私たちが感じたのは、「点数だけでは測れない学びの姿」でした。
この面談は、「できていないこと」を責めるのではなく、「この子の中にどんな可能性があるのか」を一緒に見つけ直す対話の時間だったと感じています。
今回はその内容を振り返りながら、子どもの学びについて考えてみたいと思います。
- 1.問題文に手が出せなかった国語のテスト
- 2.「理解の土台」がまだ定まっていない
- 3.合っていなかった塾のスタイル
- 4.小さな「できた」が見えてきた
- 5.中学受験という言葉との距離感
- 6.次の面談までにできること
- 7.最後に:読んでくださったあなたへ
- 読者への問いかけ
もくじ
1. 問題文に手が出せなかった国語のテスト
小学生全国統一テストを受けた娘。特に国語の問題は、文章の意味が分からず、まったく手が出せなかったとのこと。
問題に取り組めないまま時間が過ぎ、結果は300点中25点。
普段から語彙力や読解の面で課題を感じてはいましたが、テストという“形式”の中で、それがよりはっきり見えてきた形でした。
2. 「理解の土台」がまだ定まっていない
課題は国語だけでなく算数にも表れています。足し算・引き算といった基本的な計算が定着しきっておらず、問題の入口でつまずいてしまう。
でもこれは、「がんばっていないから」ではなく、「どうすれば覚えられるか・理解できるか」の土台がまだ定まっていないから。
面談で先生が話してくれたピアノの話が印象的でした。
-
“ピアノはドレミを色で覚えている。色がないと音がつながらない”
つまり、視覚的なヒントや手がかりがあると記憶に残る。でも言葉や数字のように抽象度が高くなると、一気にわかりにくくなる。
「わかるための工夫」や「学びの入り口」を一緒に探すことが、今の娘には必要なのかもしれません。
3. 合っていなかった塾のスタイル
以前、娘はマンツーマン形式の塾に通っていました。一見すると「丁寧に見てもらえる」「個別だから成長できる」と思いがちですが、実際にはその子に合わせた教え方がされていませんでした。
先生いわく、
-
“できて当然、できないならもっとやれというスタンスが根底にある”
努力をしても成果が出ないと、「自分はだめなんだ」と感じてしまうのが子どもです。
特に印象的だったのは、指導者が子どもの成長スピードや現在地を確認せず、「普通はできる」「平均的な小学生ならできるはず」という基準で対応していたことでした。
叱ること自体は決して悪いことではありません。ただ、「なぜできないのか」への想像や理解がないまま、アベレージ通りに扱ってしまうことが、逆にその子の伸びる可能性を止めてしまうのではないか。
私はそこに大きな違和感を覚えました。
個別指導だからといって必ずしも“その子に寄り添ってくれるわけではない”という現実を知ったのは、今回の大きな学びのひとつでした。形式ではなく「その場の関わり方」が子どもの未来を左右するのだと痛感しています。
だからこそ、本人が「つらい」と感じる前に、学びの環境が合っているかどうかを丁寧に見極めていく目線を、これからも持ち続けたいと思っています。
4. 小さな「できた」が見えてきた
そんな中でも、最近の娘には変化が出てきました。
たとえば、選択肢形式の問題(あ・い・うなど)には、少しずつ答えられるようになってきたとのこと。
まだ記述問題には取り組めなくても、「選んで答える」という基本動作が芽生えてきたのは大きな一歩。
また、娘が「テストが楽しい、嫌いじゃない」と言っていたこと。私はその返答に驚いた。
普通なら、テストができないことで、「やる気が落ちる」「テストが嫌になる」こんなふうになると思うのですが、娘にはそれが起きていない。
苦手なはずなのに、完全に拒否はしていない。その感覚は、これから“好きになる芽”につながる大切なサインかもしれません。
5. 中学受験という言葉との距離感
面談では「中学受験」「進学塾」という話題も出ました。
でも、娘はいま進学塾の入塾テストを受けられる状況にはありません。現実的に、中学受験を選択肢にするのはまだ難しい段階です。
それでも先生はこう話してくださいました。
完全に線を引かなくていい。つながりを小さくでも持ち続けることが大切です。
「今の実力では無理」と切り捨てるのではなく、今の場所から少しずつ「できる」を増やして可能性を探していく。
その考え方に、私はとても安心しました。というのも、「今はまだその段階じゃない」と言われるのではと構えていた自分がいたからです。
できないことを突きつけられて落ち込むよりも、「関わりを持ち続けていいんだよ」と言ってもらえたことで、目の前の娘の歩みにもう一度素直に向き合ってみよう、そんな気持ちになれました。
焦らなくていい、でも立ち止まらなくていい。
その間にある現実的な視点を先生からもらえたことが、私にとっては大きな救いでした。
6. 次の面談までにできること
7月に、もう一度先生と面談を予定しています。
それまでの間に、私たち親としてできることを考えました。
・小さな「できた」に気づいて褒める
・テストを嫌いじゃないという気持ちを伸ばす
・一緒に取り組める楽しい学習体験を増やす
・点数よりも「前よりできるようになったこと」を大切にする
子どもにとっての「学ぶ」が、自信や希望につながるような関わりを、これからも模索していきたいと思います。
7. 最後に:読んでくださったあなたへ
「このままで大丈夫かな」「うちの子、遅れてるのかも」そんな気持ちを持つ親御さんは少なくないと思います。
私もまさにそうでした。
でも、子どもはまっすぐには育ちません。ときには止まり、ときには寄り道しながら、少しずつ「自分のペース」で育っていきます。
今回のテストも、きっかけのひとつでしかありません。
点数に振り回されすぎず、今のわが子にとっての「一歩先」を一緒に見つけていく。そんな姿勢をこれからも大事にしていけたらと思います。
読者への問いかけ
・お子さんが最近“できるようになった”ことは何ですか?
・「点数」以外で、お子さんの成長をどう見つけていますか?
・今の学びの場は、お子さんに“合っている”と感じますか?