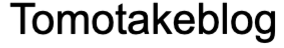【MBTIと自己理解】伝わらない『当たり前』を構造から読み解く
「自分のことなのに、自分がよくわからない。」
そんな違和感を抱えたまま、誰かとの関係に疲れたり、思うように動けなかったり。
それでも日々は続いていく。
MBTIというタイプ論に出会ったとき、
“ああ、自分ってこういう人間だったんだ”と一瞬納得できた気がした。
けれどそれだけでは、現実はあまり変わらなかった。
「INTJだから計画的」「ENFPだから自由奔放」
そうしたラベルで人を語ることに、少しずつ違和感が募っていったのです。
MBTIの本質は、タイプの分類ではなく、
「自分が世界をどう認知し、どう反応しているか」を理解する“レンズ”にあります。

このブログ記事では私自身(INTJ)が日常の中で感じた“ズレ”や“伝わらなさ”を起点に、
MBTIを通して自分と他者の思考構造の違いをどう受け止めてきたかを丁寧に言語化していきます。
この記事は「診断の解説」ではありません。
問い直しながら、自分の「当たり前」に深く向き合う旅の記録です。
あなたが感じているその違和感の正体に、この記事が少しでも近づけたら幸いです。
もくじ
- 第1章:【MBTI】は「性格診断」ではなく【認知のレンズ】である
・なぜMBTIが重要なのか?
・私(INTJ)の場合
・MBTI - 第2章:INTJとしての“当たり前”は、なぜ伝わらないのか
- 第3章:相手が見ている現実は、自分と違う【地図】の上にある
- 第4章:職場でこじれるのは、タイプと立場と【成果主義】のトライアングル
- 第5章:本当の【自己理解】は、葛藤の構造を知ること
- 第6章:タイプの違いに気づいたからこそ、【他者理解】が深まった
- 第7章:MBTIを“診断”から【人生のレンズ】に変える実践法
- 第8章:自分の【当たり前】が、世界を変えるレンズになる
- よくある質問(Q&A)
- まとめ|「自分の当たり前」が、世界を読み解くレンズになる
第1章:【MBTI】は「性格診断」ではなく【認知のレンズ】である

MBTIは、あなたの性格を「当てる」ものではありません。
本当の価値は、あなたの認知スタイルを発見することです。
つまりこれは、自己理解の深さを手に入れるレンズなのです。
なぜMBTIが重要なのか?
自分のことは、自分が一番わかっている。
そう思っていても、
・なんでこんなに不安になるのか
・なぜすぐ反発してしまうのか
・どうして行動できないのか
そんな「自分への違和感」を、説明できないまま抱えていませんか?
MBTIは、この“自分でも説明できない感覚”に、認知構造という視点でヒントを与えてくれます。
私(INTJ)の場合
INTJタイプ
・主機能は【内向直観(Ni)】
・補助機能は【外向的思考(Te)】
この組み合わせを使う私は
・何かを見聞きした瞬間に、全体像や未来の形を思い描いてしまう
・そのイメージが明確になるまで、行動に移すのが怖い
・何か求められた時に自分のルールを外れると、ストレスや苛立ちを感じやすい
こういった傾向は、本人にとっては「普通」でも、
相手からは「遅い」「慎重すぎる」と映ることがあります。
他のタイプから
「何考えてるかわからない」
「持論が強い」
このような言葉をもらうこともしばしばあります。
でも、ズレの正体を理解できたとき、自分への信頼感が少し戻ってくるのです。
MBTI
MBTIは単なる分類ツールではありません。
「なぜ自分はこう感じ、こう選ぶのか?」という問いに、言語化された地図を与えてくれるものです。
MBTIが自己理解に役立つ3つの理由
・「反応や行動」の背後にある認知のクセを見抜ける
・自分と他人の地図の違いに気づける
・「間違っているから直す」ではなく「らしさを活かす」発想ができる
問い
・あなたが最近「自分にがっかりした場面」はどんなときでしたか?
・それは本当に“悪い癖”だったのでしょうか?
・それとも、あなたの認知スタイルの現れだったのかもしれません。
次章では、INTJである私が実際に経験した
「自分の当たり前が通じなかった出来事」について、MBTIの視点で深掘りしていきます。
おすすめ
・MBTIを通して気づいた、自分の「当たり前」は他人の「不思議」|note
・INTJとして生きるということ|ブログ
第2章:INTJとしての“当たり前”は、なぜ伝わらないのか
自分では普通にやっていることなのに、相手から見ると「なぜそんなことをするのか」と不思議がられる。
それはただの価値観の違いではなく、思考や認知の『スタート地点』が異なるからかもしれません。
INTJというタイプを持つ私は、その「ズレ」に長年悩まされてきました。
自分の体験・違和感
たとえば、会議での場面
私は「このプロジェクトの目的は何か」「どういう順序で進めれば無駄が減るか」をまず考えます。
全体を俯瞰し、起こりうる問題とシナリオを構造化してから発言したい。
でも、多くの人は目の前の課題にすぐ反応する。
出てきたアイデアに対して、「面白そう!やってみよう!」と前向きに動き出す。
それを見て私は戸惑うのです。
「え、それって今決めること?」「前提合ってる?」
すると、“慎重すぎる”“理屈っぽい”と言われる。
構造的理解(MBTI視点)
INTJの主機能は【内向直観(Ni)】
物事の意味や構造、未来の因果を“ひとつの筋道”として捉えようとすます。
点と点が繋がることでドライブする。
私は何かを考えるとき、「全体を見てからピースをはめる」ように判断します。
反対に、たとえばESFPなど外向的感覚(Se)タイプは、「目の前の現実から試していく」ことをします。
どちらが正しい、という話ではありません。
使っている“レンズ”が違うだけ。
でも、認知機能の違いを知らないまま関わると、
そのズレは、まるで“人格否定”のように響いてしまうのです。
気づき・学び
私はしばらく、「自分のやり方が正しい」と思っていました。
でも、それではいつまでも相手と平行線のまま。
MBTIを通して相手のタイプや認知スタイルを知ったとき、
ようやく私は「自分の視点も偏っていた」と気づけました。
それ以来、こう問いかけるようにしています。
-
「私の“正しさ”は、どの機能に基づいている?」
「相手の行動は、どんな認知パターンから出ている?」
この問いがあるだけで、議論も会話も柔らかくなる。
相手を“変えよう”とする前に、“見え方の違い”を尊重する余裕ができたのです。
問い
・あなたが「わかってもらえなかった」経験は、どんなときでしたか?
・それは本当に、あなたのやり方が“おかしかった”のでしょうか?
それとも
あなたと相手が、違う地図を持っていただけなのかもしれません。
この第2章では、「ズレ」の原因が“性格”ではなく“認知の出発点”にあることをお伝えしました。
次章では、「相手の地図」に興味を持てた瞬間の変化について綴っていきます。
おすすめ
・INTJのストレスパターンと回復方法|ブログ
第3章:相手が見ている現実は、自分と違う【地図】の上にある
かつての私は、「どうしてこの人はこんな行動をするんだろう?」と、
相手の判断やテンポに違和感を感じるたびに、内心で小さくイライラしていました。
・「もっと考えてから話してほしい」
・「順序がおかしくないか?」
・「なぜ急に動けるの?」
でも今は、こう思います。
「きっと、見ている“地図”が違うんだな。」
体験・違和感
ある打ち合わせで、私は長期計画の構造を説明していたつもりでした。
全体のゴールと、そのために必要な工程、注意すべきリスク…
相手の発言の裏にある意図も予測して、丁寧に順を追って話していました。
でも、返ってきたのはこういう言葉
-
「ちょっと難しくない? とりあえずやってみてからでよくない?」
「そんな先のこと考えても、今は意味ないでしょ」
私はそこで話すのをやめました。
「伝わらないな」と思ったし、少し傷ついたのも本音です。
構造的理解(MBTI視点)
このとき、私と相手は“違う地図”をもとに会話していた。
MBTI的に言えば、私はNi(内向直観)+Te(外向的思考)の地図を広げていた。
未来の構造を見て、ロジックで判断しようとしていた。
一方、相手はおそらくSe(外向的感覚)+Fi(内向的感情)タイプ。
今この瞬間の状況に反応し、自分の感覚と価値観を信じて動く。
このとき私たちは、会話をしているようで、認知の地図の前提がまったく違っていたのです。
気づき・学び
MBTIを学ぶまでは、「なんでこの人は理解できないんだろう?」とずっと考えていました。
でも、今は問いが変わりました
「この人は、どんな認知地図の上で話してるんだろう?」
この問いを持つようになってから、
私は相手の発言に「違和感」よりも「興味」を持てるようになりました。
そして気づいたのです。
相手の“正しさ”を疑うのではなく、相手の“前提”を理解しようとすること
。
それが、関係を壊さずに深める第一歩なのだと。
問い
・あなたが「なぜこの人はこんな言い方をするのか?」と感じたとき、
・それは本当にその人の問題だったのでしょうか?
もしかすると
その人は、あなたとは違う【認知の地図】をもとに話していたのかもしれません。
次章では、この“地図の違い”が、職場の中でどのように複雑化し、
特に【成果主義】の文化と絡むことで、どんな“摩擦”を生んでいるのかを掘り下げていきます。
おすすめ
・相手の気持ちがわからないときに考えたいこと|note
・INTJとESFPの違いを通じて見えた、関係性の構造|ブログ
第4章:職場でこじれるのは、タイプと立場と【成果主義】のトライアングル
職場で感じる人間関係の“やりづらさ”
それは単なる性格の不一致だけではありません。
私がMBTIを学んで気づいたのは、
「立場・評価制度・タイプ」この3つが交差すると、認知の違いは摩擦に変わるということでした。
自分の体験・違和感
たとえば、こんな場面がありました
私の上司は「とにかくスピード!成果!」を重視するタイプ。
その場の判断、瞬時の対応、表に見える数字やアクションが評価の軸でした。
でも私は、どこかで納得ができなかった。
「中身のないまま走っても意味があるのか?」
「論理が崩れていたら、それは成果とは呼べないのでは?」
私は反発こそしなかったけれど、心の中ではモヤモヤしていました。
まるで、自分の“見ているもの”が軽視されているような、そんな感覚。
構造的理解(MBTI × 立場 × 劣等機能)
このとき起きていたのは、単なる性格のズレではありません。
・私(INTJ)は【Ni-Te】優位で、「未来の構造」と「論理的判断」を大切にする
・上司は【Se-Te】傾向が強く、「今の現実」+「成果を出す即時性」が優先
つまり、同じ“Te(外向的思考)”を使っていても、何に基づいて判断するかが違っていたのです。
さらに職場という環境では、
・立場が上の人の「認知スタイル」が標準とされる
・成果主義が強まると、「目に見えるパフォーマンス」に偏りやすい
・結果、自分の劣等機能(私にとってはSe:即応性)が否定されるように感じる
これが、職場での“しんどさ”の正体でした。
気づき・学び
MBTIと発達理論を交差させて考えることで、
私は「このモヤモヤは、自分のタイプが未熟だからではない」と知れました。
むしろ、自分が大事にしている価値が、今の職場文化とズレていただけだった。
そこに無理やり合わせようとすればするほど、苦しくなるのは当然だったのです。
その後、私はこう問い直しました。
-
「この環境で求められている“成果”は、私の認知とどう違う?」
「相手に合わせるだけでなく、自分の判断軸をどう守る?」
この問いができるようになってから、
必要以上に自分を責めることが減り、相手の行動にも一定の理解を持てるようになりました。
問い
あなたが職場で「伝わらない」「評価されない」と感じるのは、本当にあなたの“努力不足”でしょうか?
もしかすると
あなたの大事にしている認知スタイルと、職場の成果の定義がズレているのかもしれません。
次章では、そうした葛藤を繰り返す中で気づいた、
“本当の自己理解”とは何かについて、より内省的に深掘りしていきます。
おすすめ
・INTJの習慣設計ラボ|構造的継続を探る記録|note
・INTJが記事が書けない本当の理由|ブログ
第5章:本当の【自己理解】は、葛藤の構造を知ること
自己理解という言葉は、しばしば「強みを知ること」や「性格の特徴を整理すること」として使われます。
でも、私が実感しているのは
本当の自己理解は、“なぜ自分が葛藤するのか”を知ることにある、ということです。
それは、感情や反応の表層ではなく、
もっと奥にある“認知パターン”を見つめ直す旅でした。
自分の体験・違和感
私は、何かを決めるときに「慎重すぎる」「もっと直感で動いたら?」と言われることが多々ありました。
でも自分の中では、直感で決めることのほうが怖かった。
未来の流れが見えないまま動くのは、まるで目隠しで歩くような不安。
それなのに、「早く決めろ」「なんで迷うの」と言われるたびに、
“自分のままでいてはいけない”ような感覚になっていました。
構造的理解(認知のループと自己批判)
MBTIを通じて、私はこの葛藤が「性格の弱さ」ではないと知りました。
私の主機能は【Ni】:未来を構造化することに強く働く認知です。
その分、【Se】(目の前の感覚的な情報への即応性)は“劣等機能”として出てきます。
葛藤の多くは、この“劣等機能”を使わなければならない場面で起きていたのです。
・Seが求められる場面(すぐに動く、即興対応)で
・Ni主導の私は不安・混乱・自己否定を感じる
そしてさらにやっかいなのは、
その混乱状態に陥ると、補助機能の【Te】(外向的思考)が働いて、
「合理的に動けていない自分」を責めはじめる。
この一連の流れは、認知機能の“負のループ”**です。
気づき・学び
私はある日、このループに気づいてハッとしました。
-
ああ、私は「動けない」のではなく、
「自分のやり方を否定されたまま、動こうとしていた」んだ。
それ以来、私は迷ったときにまずこう問いかけるようにしています。
・「私は今、どの機能を“否定された”と感じている?」
・「本当に必要なのは“変わること”ではなく、“自分の構造を守ること”じゃないか?」
この問いがあるだけで、
迷いの意味が変わる。
自己否定ではなく、“認知の選択肢”を再構成する機会に変わるのです。
問い
・あなたが「自分が嫌になる」瞬間。
・それは、あなた自身の性格が“間違っている”からでしょうか?
もしかすると
あなたの中で、認知機能同士が葛藤していたのかもしれません。
次章では、タイプの違いを知ったことで、
どうやって【他者理解】が深まり、関係性が柔らかくなっていったかを描いていきます。
おすすめ
・INTJの習慣設計ラボ|行動できないのは意志の問題じゃない|note
・INTJの思考と行動の葛藤構造を解説|ブログ
第6章:タイプの違いに気づいたからこそ、【他者理解】が深まった
MBTIを学び始めた頃、私は「まず自分のことを知りたい」と思っていました。
けれど、あるとき気づいたのです。
-
自分のことを深く理解しはじめると、自然と“他人のこと”が気になりはじめる。
・「なぜあの人はそう言うのか?」
・「どうしてあんなふうに動けるのか?」
その“わからなさ”を、恐れずに見つめられるようになったのは、MBTIというレンズを手に入れたからでした。
自分の体験・違和感
以前の私は、人の言動に違和感を覚えたとき、
心の中で相手を“判断”してしまうクセがありました。
・「軽すぎるな…」
・「この場面でそれ言う?」
・「もっと先を見て動いてほしい」
特に、目の前の状況にすぐ反応して盛り上がるタイプの人たちに対して、
「それって意味あるの?」と冷めた視線を向けてしまうことがありました。
でも、MBTIを知ってから、その見方が徐々に変わっていったのです。
構造的理解(他タイプの“自然さ”を認める)
私が違和感を覚えた相手は、たとえば【ESFP】のようなタイプかもしれません。
Se(外向的感覚)を主機能に持ち、目の前の楽しさ・可能性・反応に強く反応するタイプ。
私(INTJ)はNi(内向直観)主導なので、
・今より「未来」
・外より「内」
・楽しさより「構造の整合性」
このように、見ている方向も重視している情報もまるで違っていたのです。
違和感の正体は、「正誤」ではなく「焦点のズレ」でした。
そのズレに気づいたとき、私ははじめて、
相手を“否定”ではなく“観察”できるようになったのです。
気づき・学び
タイプの違いを知ってから、私は少しずつ変わりはじめました。
・相手の反応に「背景がある」と思えるようになった
・自分と違うやり方を「不正解」と決めつけなくなった
・そして、無理に“わかろうとしない余白”も持てるようになった
特に印象に残っているのは、
以前苦手だったある上司に「最近は話しやすくなった」と言われたことです。
私は何も“変わっていない”つもりだったけれど、
きっと私の“構え”が変わったのだと思います。
問い
・あなたが「どうしても理解できない」と感じている相手。
・その人のやり方に、あなたはどんな“正解”を当てはめているでしょうか?
もしかすると
あなたの「正しさ」の奥に、“自分らしさの守り”があったのかもしれません。
次章では、MBTIを“知って終わり”にせず、
日常の中でどう活かし、自己理解と他者理解をつなげていくかの実践に踏み込んでいきます。
おすすめ
・ENFPとESTJの認知スタイルの差と距離感|ブログ
第7章:MBTIを“診断”から【人生のレンズ】に変える実践法
「私はINTJです」
「あなたはENFPっぽいよね」
MBTIを知ると、そんなふうに“ラベル”で会話が盛り上がることがあります。
でも本当の意味でMBTIを活かすには、「知っている」から「使っている」状態へ進む必要があります。
この記事の終盤では、
MBTIを“人生に活かすレンズ”として使うための具体的な実践法についてお話しします。
自分の実践・経験からの気づき
私はある時期から、MBTIを使って「自分を説明する」よりも、
「今この場面にどう機能を使っているか」を観察するようになりました。
たとえば、こんなふうに
・会話のテンポが合わないとき → 「今、相手はSeで動いてるな」
・モヤモヤするとき → 「今、劣等機能が刺激されてる?」
・無性に否定したくなったとき → 「私のTeが優勢になってるかも」
こうして内面の動きを“言語化”するようになると、
目の前の状況と、自分の反応が“分離”され、冷静さが戻ってくるのです。
メタ認知的視点への移行
構造的活用法:日常の3場面でMBTIを活かす
MBTIは、日常のあらゆる場面に活かすことができます。
以下に、私自身が使っている3つの場面別の問いをご紹介します。
① 人間関係のすれ違いで
「この人は“何をもとに判断している”タイプだろう?」
→ 主機能や補助機能を意識するだけで、会話が噛み合いやすくなる
② 自分の行動に迷ったとき
「今の私は、どの機能に引っ張られている?」
→ 主機能と劣等機能のズレを自覚すれば、反応ではなく選択ができる
③ 相手の行動にモヤっとしたとき
「“おかしい”と感じるのは、どの価値基準がズレているから?」
→ 自分のTeやFiなど、評価軸を確認する習慣を持つ
気づき・学び
MBTIの真価は、ラベルではなく、自分の「思考・感情・行動」の背景に構造を持たせられるところにあります。
それは、自己否定でも、相手の正当化でもない。
「今、自分はどういう認知で世界を見ているか?」という自覚です。
その問いを持つことで、
・無意識に動いていた反応が落ち着き
・選択肢が増え
・自分にも相手にも、少しだけ優しくなれる
私にとってMBTIは、“型にはめる道具”ではなく、
世界を立体的に見るためのレンズになりました。
問い
・あなたは今日、どんな場面で「らしくない自分」に出会いましたか?
・そのとき、どんな認知が働き、何が苦しかったのでしょうか?
MBTIの知識が、
あなた自身を責めるためではなく、理解するために使われますように。
次章では、これまでの記事全体を振り返りながら、
“自分の当たり前”が持つ力と、違いを抱きしめる視点について、
あなたへの言葉を綴って締めくくります。
おすすめ
・朝の思考メンテナンス|note
・MBTIの認知機能を生活に活かす方法|ブログ
第8章:自分の【当たり前】が、世界を変えるレンズになる
「どうして、わかってもらえないんだろう」
「なぜ私は、こういうふうに感じてしまうんだろう」
そんな問いを繰り返すなかで、私はMBTIというフレームと出会いました。
それは、自分を守る“診断の盾”ではなく、世界を読み解く“レンズ”になっていきました。
この章では、その旅路の最後に見えたことを、あなたに言葉として残したいと思います。
自分の実感・まとめ
私の「当たり前」は、
・構造を考えてから動くこと
・無駄を避けて最短ルートを描くこと
・感情よりも意味に注目してしまうこと
これらは長らく「やりすぎ」「堅い」「冷たい」と言われてきました。
そのたびに「このままではいけないのか」と迷い、疲れていました。
でも今は、少しだけ違う景色が見えます。
認知のレンズが変えるもの
MBTIが教えてくれたのは、
「自分の感じ方には、理由がある」という安心感でした。
そして同時に、
「相手の感じ方にも、同じように理由がある」という敬意でもあります。
世界はバラバラです。
だからこそ、自分の“当たり前”を言葉にすることが、
誰かにとっての“地図”になるかもしれない。
あなたが感じる「違和感」や「わかってもらえなさ」は、
きっと誰かの“わかってもらえた”につながる可能性を持っています。
最後の問い
・あなたの「普通」は、誰にとっての「謎」でしょうか?
・そしてその謎は、誰かにとって、何をひらく鍵になるでしょうか?
この記事では、MBTIという枠組みを通して、
自分自身の思考・感情・反応の“構造”を読み解いてきました。
それは決して「タイプで決めつける」ためではなく、
「違いを対話のきっかけに変える」ための理解です。
あなたの“当たり前”を、
どうかあなただけが否定しないでください。
そのまなざしが、世界を少し優しく、柔らかくしてくれるから。
おすすめ
・ISTPとINFPの価値観の違い 劣等機能から見るすれ違い|note
・MBTIで鬼滅キャラを読み解くと見える“価値観とズレ”|ブログ
よくある質問(Q&A)
Q1. MBTIを学んでも、実生活で活かせている実感がありません…
A. MBTIは「知るだけ」では変化が起きにくいです。
大切なのは、日常の中で自分の思考・反応・選択に「どの機能が働いているか?」を意識すること。
意識できると、感情に流されずに自分の反応を“観察”できるようになります。
そこから実践と変化が生まれます。
Q2. 他人のタイプがわからない場合、どう理解すればいいですか?
A. タイプを特定するより、「どの情報を重視しているか?」を観察するほうが実践的です。
たとえば:
・今の感覚に強く反応する → Se優位の可能性
・感情や調和を重んじる → FiやFeの傾向かも
“タイプ名”より、“認知のクセ”を見る視点を持つことで、コミュニケーションのズレが減っていきます。
Q3. INTJとして生きづらさを感じています。改善のヒントはありますか?
A. INTJの「未来から逆算して最適化する」性質は、短期決断や感情的判断を求められる場面で誤解されやすいです。
まずは、自分の認知スタイルを否定せず、“強みと苦手”の構造を理解すること。
次に、周囲との認知の違いを「違い」として受け止められるようになると、少しずつ楽になります。
Q4. 自己理解が深まっても、現実の行動に変化が出ません…
A. それは正常なプロセスです。
自己理解は“内面の地ならし”であり、行動はその後に自然と整ってくるものです。
無理に変えようとするより、「今の選択は、どの機能に基づいている?」と内省を続けることで、
自分らしい行動スタイルが徐々に明確になります。
Q5. MBTIはただの占いや性格診断とどう違うのですか?
A. MBTIの核は「認知機能」という“情報の捉え方と判断の傾向”を構造で捉える理論です。
単なる「当てもの」ではなく、人間の思考・感情・行動のプロセスに迫る体系的なモデル。
使い方次第で、対人関係・自己理解・キャリア選択に深い気づきを与えてくれます。
まとめ|「自分の当たり前」が、世界を読み解くレンズになる
私たちは日々、「どうして伝わらないのか」「なぜわかってもらえないのか」という葛藤を抱えながら生きています。
その違和感の正体に、MBTIという“認知の構造”からアプローチしてきたのが本記事のテーマでした。
本記事で伝えたかったこと
-
・MBTIは「性格診断」ではなく、「思考と反応の構造」を知るレンズ
・INTJというタイプを通じて、自分の当たり前が他者には通じない経験を描写
・葛藤や摩擦の裏には、認知機能や環境、成果主義などの複雑な交差がある
・自己理解とは、自分の“感じ方・選び方・迷い方”に納得すること
・MBTIを知識で終わらせず、実践で“自分と他者を観察する問い”へと変えていくことが鍵
メッセージ
あなたが持っている「違和感」や「当たり前」は、決して間違いでも未熟さでもありません。
それは、あなたの認知のスタイルが大切にしているものの現れです。
自分を否定する前に、
「なぜそう感じるのか?」「なぜそう選ぶのか?」と
問い直してみてください。
その問いが、あなた自身の視点を育て、
やがて他者との間にあたたかな理解をもたらしてくれるはずです。
次へ
・あなたの“普通”は、誰にとっての“未知”だろう?
・その違いを、どんな対話の入り口にできるだろう?