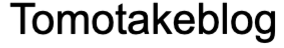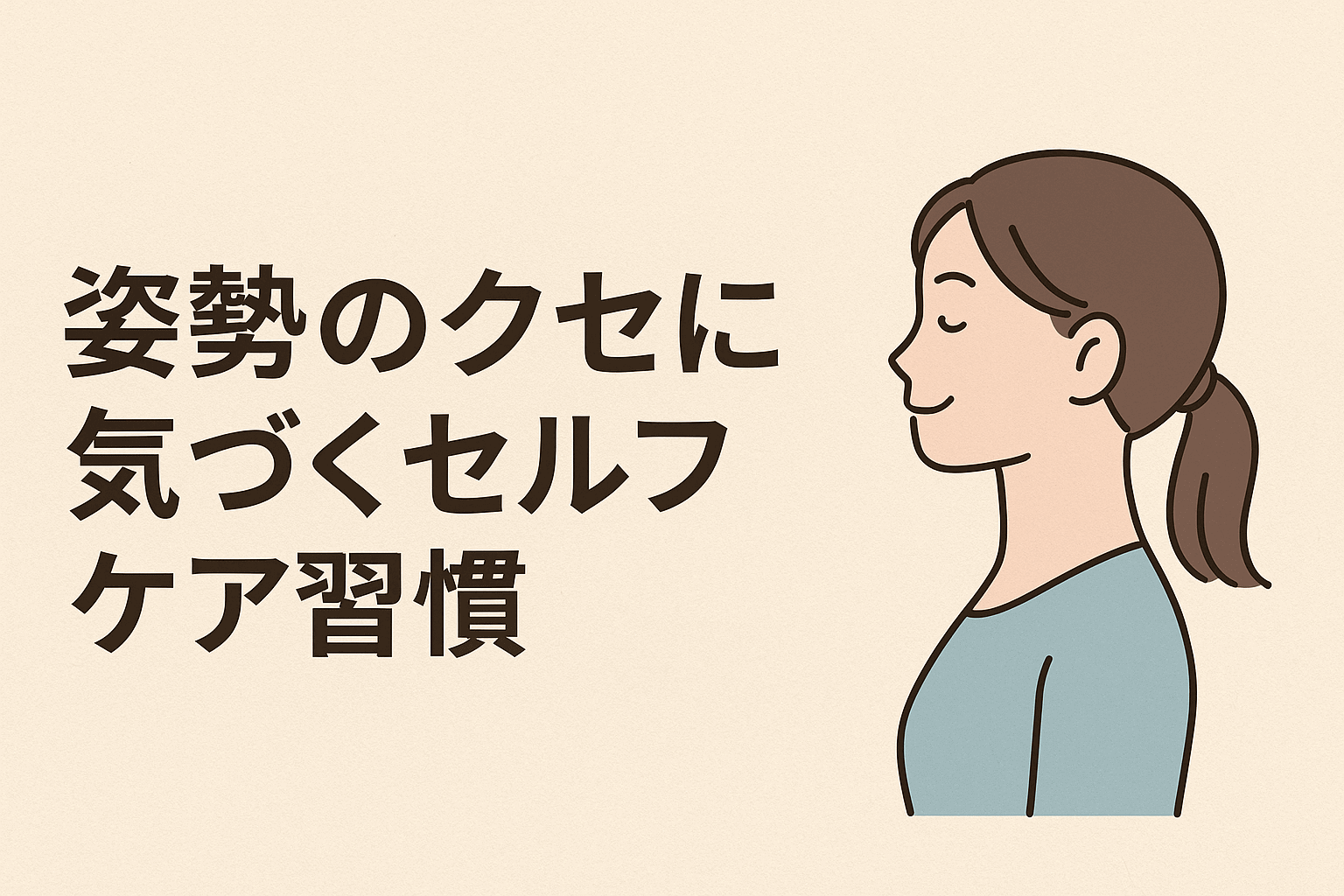「良い姿勢」が疲れる理由とは?姿勢分析とセルフケアで解消
「自分では“いい姿勢”のつもりなのに、なぜか疲れやすい」
「リラックスできていない感じがする」
そんな違和感を感じたことはありませんか?
私自身、ずっと“まっすぐ立っているつもり”で日々を過ごしていました。
でも、ふと鏡に映る自分を見た時、「あれ?こんなに傾いてたんだ…」と驚いたのを覚えています。
姿勢は無意識のうちにクセづいていきます。
しかも、その“クセ”は自分では気づきにくく疲れや不調のサインとして現れることも少なくありません。
この記事では、私自身が姿勢分析を通して「体の傾き」に気づき整え始めた過程をセルフケア視点でまとめました。
日常のちょっとした違和感を手がかりに、自分の身体と対話するヒントになれば嬉しいです。
もくじ
- 姿勢が“崩れている”ってどういうこと?
・「なんか疲れる」は体からのサイン
・一般的な“良い姿勢”が合わないこともある - 自分のクセに気づく|姿勢分析の視点
・姿勢は無意識のクセがつくり出す
・姿勢分析で見る5つのチェックポイント(足〜頭)
- ティルト(傾き)
- シフト(左右のズレ)
- ローテーション(ねじれ)
- ベント(前後屈)
- ローテンション(筋緊張の偏り) - 姿勢を整えるためのセルフケア習慣
①足元からの観察|姿勢は“足で決まる”
②呼吸の深さと骨盤の傾きの関係
③日常姿勢を“3秒”観察するクセをつける - 私が姿勢に気づいて変わったこと
・「これが普通」と思っていた姿勢は、頑張りすぎの姿だった
・姿勢が整うと、頭も静かになっていった - 姿勢を整えるのは“未来の体”へのギフト
・姿勢は5年後・10年後の自分をつくる
・完璧じゃなくていい。“今の自分”を知ることがスタート - まとめ|姿勢を変えるのではなく、気づきが整え始める
姿勢が“崩れている”ってどういうこと?
姿勢が悪い、体が歪んでいると言われても、自分ではピンとこない。
私も最初はそうでした。
けれど、疲れやすさや肩こり、腰の重さといった「なんとなく不調」に目を向けた時、その裏にある原因として“姿勢のクセ”が見えてきたのです。
「なんか疲れる」は体からのサイン
「最近、なんとなく疲れが取れない」
「長時間座っていると腰や肩が痛くなる」
そんな風に感じたことがある方は多いと思います。
でも、それが「姿勢の崩れ」から来ているとは、なかなか気づきにくいものです。
私自身も「仕事の疲れかな」と思っていた違和感が、実は姿勢の歪みからきていることに気づいたのはかなり後になってからでした。
姿勢が崩れると、筋肉や骨格に余計な負担がかかります。
しかも、そうした状態が“当たり前”になると、体はその姿勢を補正するように、別の場所でバランスを取ろうとします。
結果、体全体に無理が生じ、疲れやコリとして現れてきます。
一般的な“良い姿勢”が合わないこともある
私たちはよく「背筋を伸ばして、胸を張って立ちなさい」と言われて育ってきました。
でも実際には、それがすべての人にとって“良い姿勢”とは限りません。
人それぞれ、骨格や筋肉のつき方、日常の動きのクセが違います。
だからこそ、“正しそうに見える姿勢”が、実は自分にとっては無理をしている状態の場合があるんです。。
私はピラティスや姿勢分析を学ぶ中で、「自分の姿勢が“良い”かどうかは、見た目ではなく“楽に呼吸できるか”“力まずに立てるか”で判断するのがいい」と感じるようになりました。
出典:日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌
自分の姿勢がどうなっているのか、まずは“気づくこと”がセルフケアの第一歩になります。
自分のクセに気づく|姿勢分析の視点
無意識のうちに形作られた姿勢のクセ。
それに気づくには「自分を観察する目」が必要でした。
どこが傾いている? どちらに流れている? そうした問いかけを自分の体に向けるようになってから、初めて「本来の自分の姿勢」に近づけるようになった感覚があります。
姿勢は無意識のクセがつくり出す
日々の姿勢は、「こうしよう」と思って作られてません。
日常生活の中で無意識に染みついた動きやクセによって形作られていることが多いです。
私の場合、長時間のパソコン作業や、左肩での荷物持ちのクセから、右肩が下がり、骨盤が左に流れていました。
でもそれが「自分にとっての自然な姿勢」だと思っていました。
違和感があっても「年齢のせい」「疲れかな」と流してしまいがちでした。
姿勢分析を通して
「こういう立ち方をしていたんだ」
「だから疲れやすかったんだ」
と知ることができようやく整える一歩が始まりました。
姿勢分析で見る5つのチェックポイント(足〜頭)
以下は、私が実際に姿勢分析で学んだ観点です。
・ティルト(傾き):骨盤や肩の前後の傾き(反り腰や猫背)
・シフト(左右のズレ):骨盤や肩が左右どちらかに流れている状態
・ローテーション(ねじれ):胴体や足がどちらかにねじれている
・ベント(前後屈):上体が前屈・後屈方向に偏っている
・ローテンション(筋緊張の偏り):筋膜ラインの張力に左右差がある状態
これらを足元から順にチェックすることで、自分では気づきにくかった“歪みの起点”が見えてきます。
姿勢に関する自己観察やクセの気づきは、理学療法やボディワーク分野でも推奨されている重要なアプローチです。
姿勢を整えるためのセルフケア習慣
姿勢を整えるといっても、急にストレッチやトレーニングを始める必要はありません。
まずは「観察すること」から始めてみるだけで、体との関係が変わり始めました。
①足元からの観察|姿勢は“足で決まる”
身体の土台である「足元」に注目することで、全体のバランスが整いやすくなります。
・立った時に重心はどこにあるか?
・足の裏のどこに体重がかかっているか?
私は朝起きた時と夜寝る前に、「足裏の感覚」に注意を向ける時間を作りました。
それだけでも、上半身の力みやバランスのズレに気づきやすくなったのです。
②呼吸の深さと骨盤の傾きの関係
呼吸の深さは、骨盤の傾きと密接に関係しています。
私は呼吸が浅く感じる時、骨盤が後傾して猫背になっていることが多いと気づきました。
軽く骨盤を起こして
・背中を丸めすぎず
・肩の力を抜くだけで
・呼吸が入りやすくなる
感覚があります。
③日常姿勢を“3秒”観察するクセをつける
立つ、座る、歩くなどの日常の動きの中で、「3秒だけ姿勢を感じてみる」。
・いまどこに力が入っているか?
・重心は左右で偏っていないか?
・呼吸は止まっていないか?
たったそれだけで、自分の状態に意識が向き必要以上に頑張っている自分に気づけることがあります。
この“気づきのループ”が、姿勢を根本から整えていくセルフケアの出発点です。
私が姿勢に気づいて変わったこと
姿勢のクセに気づいて整えていくと、自分の体だけでなく“心の状態”にも変化を感じました。
「自然体でいる」ってこういうことだったんだと、ようやく腑に落ちたのです。
「これが普通」と思っていた姿勢は、頑張りすぎの姿だった
以前の私は、「見た目がきれいな姿勢」を意識するあまり、常にお腹に力を入れ、肩を引いて胸を張るようにしていました。
でも、それは“緊張し続けている姿”でもあったのです。
このような無意識の緊張状態は、自律神経のバランスにも影響を与えることが知られています。交感神経が優位になり、リラックスしにくい状態が続くと、慢性的な疲労感や睡眠の質の低下につながる可能性もあります。
自分にとっての“自然体”を知ってからは、余計な力が抜け、呼吸も深くなり、結果として疲れにくくなっていきました。
姿勢が整うと、頭も静かになっていった
興味深いのは、身体の力みが抜けると、心にも変化が現れるということです。
以前の私は、頭の中で常に「〜しなきゃ」と考えてばかりで、気持ちが落ち着きませんでした。
でも、身体の姿勢が整い、無駄な力が抜けてくると、「いま、ここにいる」という感覚が戻ってきました。
呼吸が深くなり、結果的に思考もクリアになってきたのです。
マインドフルネスやボディワークにおいても、身体の感覚への気づきが心理的安定に寄与することが示されています。
姿勢を整えるのは“未来の体”へのギフト
姿勢は5年後・10年後の自分をつくる
姿勢のクセは、すぐに痛みとして現れないこともあります。
しかし、長年かけて積み重なった負担は、将来的に腰痛、膝痛、肩こりなどの慢性不調として表面化することがあります。
「いま整えておくことが、未来の自分のためになる」
そう考えることで、無理せずじっくりと姿勢と向き合うことができるようになりました。
完璧じゃなくていい。“今の自分”を知ることがスタート
大切なのは、「正しい姿勢」を手に入れることではなく、「今の自分の状態に気づくこと」。
そこから少しずつ、自分に合った整え方を見つけていけばいいのです。
「ちょっと楽になったかも」と感じられること、それがセルフケアとして継続できる鍵になります。
まとめ|姿勢を変えるのではなく、気づきが整え始める
姿勢の歪みは、誰にでもあるもの。
でも、それに“気づけるかどうか”が整え始めるきっかけになります。
私は姿勢分析を通して、自分の無意識のクセに気づき、体と対話する時間を持てるようになりました。
「なんか疲れる」
「違和感がある」
そんな感覚は、体からのサインかもしれません。
気づくことで整う。姿勢を整えることは、自分を大切にする第一歩であり、未来の自分への信頼の回復でもあるのです。