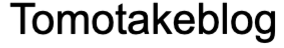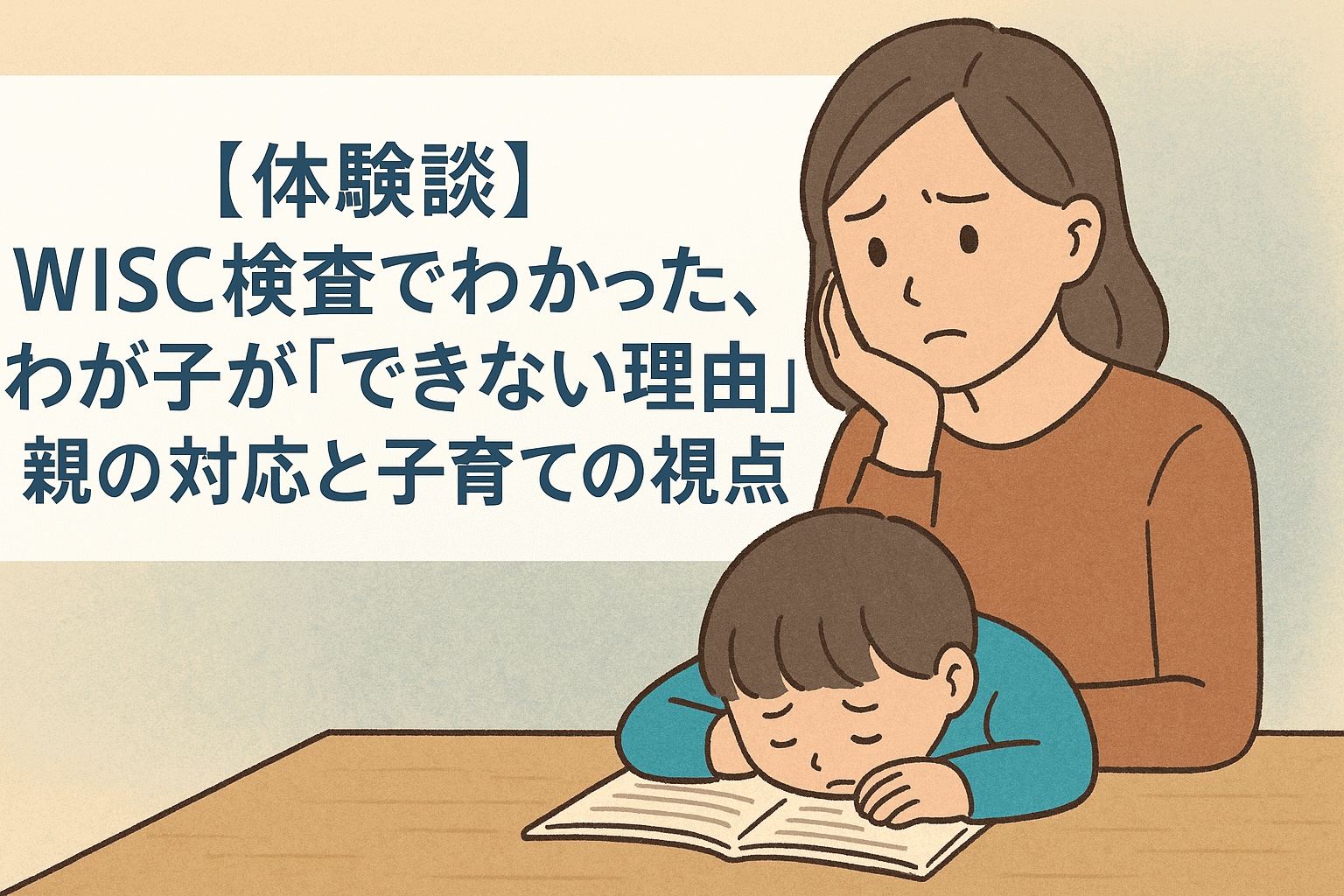【体験談】WISC検査でわかった!わが子が「できない理由」と親の対応と子育ての視点
「なんでこんなに話を聞いていないの?」
「一度言ったことを、なんで何回も忘れるの?」
「他の子はできているのに、なんでうちの子だけ…?」
そんな風に、子育ての中でモヤモヤしていた時期がありました。
わが子が怠けているように見えることもあり、つい叱ってしまったこともあります。
でも本当は、「できない」んじゃなくて、「見え方や聞こえ方が違っていた」だけだった。
そのことに気づけたのは、「WISC(ウィスク)検査」がきっかけでした。
本記事では、実際にWISC検査を受けた親としての体験と、INTJタイプの親としてどう受け止め、どう対応を考えたかを、具体的に共有します。
- はじめに:「授業についていけない理由」が見えなかった日々
- WISC検査とは?|子どもの認知特性を可視化する知能検査
- わが子の検査結果と見えてきた【認知の凸凹】
- 「見えている世界が違った」ことに、ようやく気づけた
- INTJタイプの親としての受け止め方|感情ではなく構造を理解したい
- 家庭・学校・習い事、それぞれに行った対応
- よくある誤解:「WISCでラベリングされるのでは?」
- 親自身の変化|「理解できない」から「設計できる」へ
- 子育ては“感情のやりとり”であり、“情報の設計”でもある
- まとめ:見えない特性を「理解」と「戦略」に変える
- 行動のヒント:次に取れる一歩
- 最後に:わからないまま進むより、「わかろうとする問い」を持つ
もくじ
WISC検査とは?|子どもの認知特性を可視化する知能検査
WISC(ウィスク)は、6歳〜16歳の子どもを対象とした「知能検査」です。
正式には「Wechsler Intelligence Scale for Children(第4版)」と呼ばれ、以下の4つの指標をもとに、子どもの認知スタイルを明らかにします。
| 項目名 | 説明 |
| 言語理解(VCI) | 言葉の意味理解や表現力、語彙力など |
| 知覚推理(PRI) | 視覚情報からパターンや空間関係を把握する力 |
| ワーキングメモリ(WMI) | 聞いた情報を記憶し、処理する短期記憶力 |
| 処理速度(PSI) | 視覚情報を素早く、正確に処理するスピード |
これらを総合した全検査IQ(FSIQ)も算出されますが、
本質的には「IQの高さ」よりも「どの領域に強み・弱みがあるか」が重要です。
わが子の検査結果と見えてきた【認知の凸凹】
検査の結果、わが子の全検査IQは93(平均よりやや低め)。
けれど驚いたのは、指標間の差が非常に大きかったことです。
得意分野
・知覚推理(図形・空間把握)
・処理速度(単純作業の早さ)
苦手分野
・ワーキングメモリ(聞いたことを記憶して処理)
・推理的思考(規則性や論理的な理解)
このばらつきが、日々の違和感と完全に一致しました。
「見えている世界が違った」ことに、ようやく気づけた
振り返ると、わが子は以下のような傾向を見せていました。
うまくいかなかったこと
・授業中の先生の話を理解できず、手が止まる
・指示を聞き逃して、次に何をすればよいかわからない
・長文の文章読解や、算数の文章題に苦手意識が強い
うまくいっていたこと
・ダンスの振り付けは一度見ればすぐ覚える
・ピアノは「色」や「音」で覚え、耳コピーも得意
・図工やブロック遊び、図形問題はむしろ好き
つまり、「耳から入ってくる情報処理」が弱く、
「視覚的な処理」や「動きを模倣する力」が強かったのです。
INTJタイプの親としての受け止め方|感情ではなく構造を理解したい
INTJタイプのわたしは、物事を感情で処理するよりも「構造と因果」を理解したいタイプ
「できないから支援しよう」では納得できませんでした。
私の問いは、常にこうでした
「この子が“できないように見える理由”はどこにあるのか?」
「そして、それを前提にどう支援の設計をすればいいのか?」
WISC検査は、それに対する仮説の土台と戦略のヒントを与えてくれたのです。
家庭・学校・習い事、それぞれに行った対応
家庭での工夫
・指示は短く・1つずつ
・視覚支援(タイマー、イラスト付きの予定表、ToDoリスト)
・勉強中は色ペンや図解、マッピングを多用
・目に見えるご褒美設定(例:「このプリント終わったら10分休憩」)
学校へのアプローチ
・担任の先生にWISC結果を共有し、理解を依頼
・「口頭説明のみ」ではなく、「関わり方や・サポート」の方法を共有
・必要があれば、特別支援教室や合理的配慮を相談
習い事の見直し
・学習塾や公文は「理解、聞く力」が求められるので難しかったため中断
・太鼓・ピアノ・そろばん・ダンスなど、「視覚×身体」を使うものを継続
・「得意を伸ばす習い事」に絞って選択
よくある誤解:「WISCでラベリングされるのでは?」
WISC検査というと「IQで子どもを評価するの?」と不安になる方もいると思います。
でも、実際はその逆です。
・子どもがなぜ困っているのか
・どのようにすれば理解しやすくなるのか
・苦手をどうカバーすればいいのか
を、見える形で教えてくれる手がかりなのです。
検査は“診断”ではなく“地図”だと、私は捉えています。
親自身の変化|「理解できない」から「設計できる」へ
検査結果を見たとき、もちろん一瞬は落ち込みました。
「平均より下」と言われると、不安になります。
「この子はやっていけるのか?」と未来が見えなくなる気もします。
でも、INTJのわたしにとっては、“不安の正体がわかること”こそ最大の安心でした。
原因がわかれ対応を設計できる。
構造が見えれば無駄な不安や叱責は減る。
「何をしても伝わらない…」というあのストレスが、仮説→行動の繰り返しで徐々に解消されていきました。
子育ては“感情のやりとり”であり“情報の設計”でもある
私たち親は、つい感情的になります。
でも、子どもをサポートするには、「どうすれば伝わるか?」という伝え方の設計が必要です。
・言葉だけではなく、視覚的に伝える
・長い説明よりも、具体的な一文
・曖昧な「ちゃんとして」より、「●時に机に座ってプリントを開ける」と明示する
こうした対応が、わが子の負担を減らしてくれました。
それと同時に、私たち親の「できていない自分を責める時間」も確実に減っていきました。
まとめ:見えない特性を「理解」と「戦略」に変える
子どもには、それぞれ“見え方”や“感じ方”の違いがあります。
その違いを、わたしたち親が「できない」ではなく「特性」として捉えるかどうかが、子ども自身の生きやすさに直結します。
WISC検査は、その特性を可視化するひとつのツールです。
そして、INTJタイプの親としては、そのデータをもとに戦略的に関わり方を変えていくことが可能です。
行動のヒント:次に取れる一歩
・WISC検査が気になる方は、「WISC 検査 地域名」で検索
・学校の担任やスクールカウンセラーに、気になることを相談
・支援センターや発達クリニックに相談(2年ごとの再検査も可)
・記録(メモ・図解)をとって振り返る癖をつける(INTJ的おすすめ)
最後に:わからないまま進むより、「わかろうとする問い」を持つ
私たちはまだ、完璧な対応ができているわけではありません。
でも、「なぜ?」という問いと、「こうすれば伝わるかも」という仮説があれば、関わり方は進化し続けます。
子どもの“見えている世界”を知ることが、親としてのスタート地点。
あなたとあなたのお子さんが、少しでも楽になる関係性を築いていけますように。